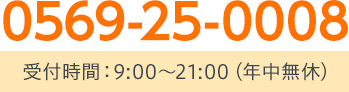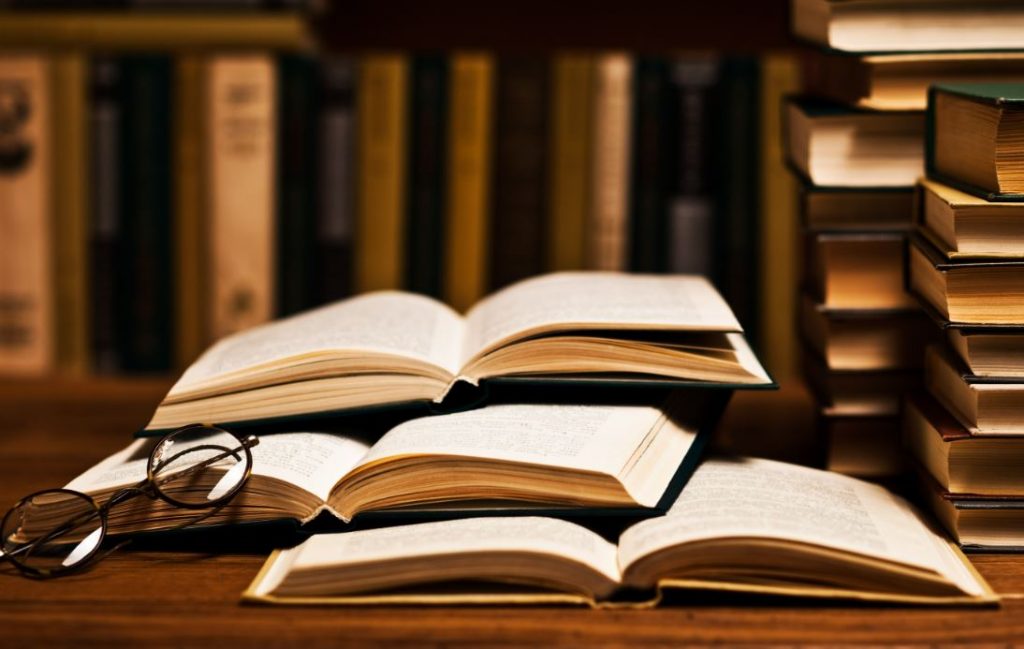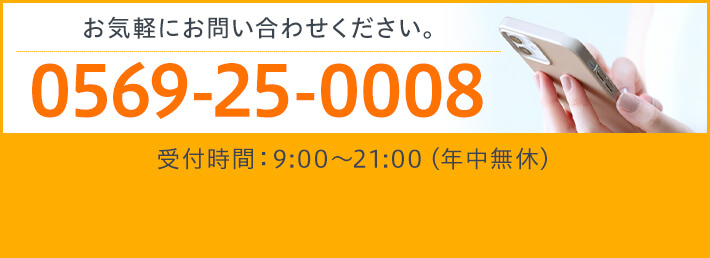業務中や通勤・退勤の途中に交通事故に遭ってしまった場合、「労災(労働災害)」となります。交通事故でも労災認定されれば労災保険が給付されるので、治療費や休業損害、慰謝料など、正しい知識を持って適切に補償を受けましょう。また交通事故の場合、加害者の自賠責保険と労災保険の関係も知っておくとよいでしょう。

交通事故と労災の関係
労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者災害補償保険法に基づく制度で、労働者が業務上や通勤によって、負傷や障害を負ったり、疾病にかかったり、又は死亡した場合に、当該労働者やその遺族に支払われる保険のことです。
雇用者は一人でも従業員を雇ったら必ず労災保険に加入しなければならず、対象者は正社員や契約社員、嘱託社員、アルバイトやパート、日雇い労働者を含むすべての従業員となります。
労災保険が適用される労災事故を一般的に「労災(労働災害)」と呼んでいます。労災保険法は、業務時間中など仕事に関係して死傷したり病気になったりした場合を「業務災害」、通勤退勤の途中に死傷したり病気になったりした場合を「通勤災害」として区別しています。
通勤途中に事故に遭ってしまった場合、労災保険が適用されます。労災保険を適用する場合、会社に届け出ている通勤経路(就業場所と自宅の往復)で事故に遭ったり、社用車で取引先に向かう途中で事故に遭ったりと、合理的な経路である必要があります。
また、交通事故が労災に該当する場合、労災保険から各種の給付を受けられますが、そのためには労基署へ「労災保険の申請」を行って労災認定されなければなりません。業務中や通勤退勤途中に交通事故に遭ったら、書類を作成して労基署へ提出し、各種給付の申請をしましょう。
また交通事故は労災事故の中でも「第三者行為災害」に分類され、これは本人や会社以外の「第三者の行為」によって発生した労災事故になります。交通事故の場合には加害者が第三者となり、第三者行為災害の場合には、労災保険申請の際に通常書類とは別途「第三者行為災害届」を提出する必要があるので注意が必要です。
労災保険から支給される補償の種類
交通事故が労災認定されると、以下のような給付金を受け取れる可能性があります。
療養(補償)給付
療養給付は、いわゆる治療費で、労働者が業務災害または通勤災害により負傷または疾病にかかり療養を必要とする場合に行われます。労災扱いになると、健康保険の場合と異なり,被保険者の窓口負担はなく、基本的に労災保険が治療費を全額支給してくれます。
休業(補償)給付
労働者が業務災害または通勤災害に係る療養のために,仕事ができず、賃金が減額されるかまたは賃金の支払いを受けられない場合に,給付される金銭です。休業給付は休業開始4日目以降から給付され、基礎賃金の8割までとなります。
障害(補償)給付
通勤災害での負傷が治らず、後遺障害が残ってしまった場合、認定された後遺障害の等級によって一時金や年金を受け取れます。
障害給付は「後遺症が残った」という状態だけでは支給されず、後遺症が「後遺障害」と認定されて初めて支給されます。認定等級が1~7級なら障害補償年金(障害年金)、8~14級なら障害補償一時金(障害一時金)として支給されます。
傷病年金
療養補償給付を受ける労働者の傷病が、療養の開始後1年6ヶ月を経過しても治癒せず、1~3級の傷病等級に該当する場合には傷病年金が支給されます。
傷病給付を受け取る手続きは被災者からの申請ではなく、労基署長の判断によります。傷害給付が支給されると休業給付は受けられません。
介護(補償)給付
労災に遭って重傷を負い介護が必要になった場合、一定の条件を満たせば介護費用が支給されます。障害補償年金または傷病補償年金の第1級の者または第2級の者(精神・神経障害および胸腹部臓器障害者の者に限る)で,常時または随時介護を要する者に支給されます。
遺族(補償)給付

業務災害または通勤災害により労働者が死亡した場合に、遺族に対して年金または一時金として給付金が支払われます。遺族補償給付には,遺族補償年金(遺族年金)と遺族補償一時金(遺族一時金)とがあり,労働者の死亡当時の生計維持関係,死亡労働者との続柄,遺族の年齢等によっていずれかになります。
葬祭料
労働者が業務上死亡した場合に、遺族に葬祭料が支払われます。31万5,000円の定額に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高いほうの額が支給されます。

自賠責保険と労災保険の関係
交通事故に遭った場合、被害者は加害者側へ損害賠償請求として、休業損害、介護費用、後遺障害に関する損害(慰謝料や逸失利益)、死亡した場合の損害(慰謝料や逸失利益)などを請求できます。
一方、交通事故が労災になると、労災保険からも治療費や休業補償、障害給付などを受け取れます。ただ、労災保険と交通事故の両方に補償がある項目については、どちらか一方しか受け取れません。
労災保険を適用すると、労災保険から治療費を全額支給してもらえます。自賠責の場合には「120万円」などの限度がありますが、労災保険には限度がないので最後まで安心して治療を受けられます。
また、労災保険では治療費の打ち切りの心配がありません。治療期間が長くなると、任意保険会社は一方的に治療費の支払いを打ち切るケースが多く、症状固定していないのに無理矢理治療費を打ち切られて困る被害者の方がたくさんおられます。
しかし、労災保険の場合は、基本的には医師の判断が尊重されるので、保険会社の判断で打ち切られる心配がありません。
労災保険の場合、休業(補償)給付が支給されます。労災保険では、休業期間中、賃金を受けない4日目から、休業1日につき平均賃金の60%の「休業(補償)給付」が支給されます。併せて、休業1日につき平均賃金の20%の「休業特別支給金」が支給されるので、合計80%の休業補償が支給されることになります。
慰謝料について
交通事故の損害賠償金には慰謝料が含まれますが、労災の障害補償給付金には慰謝料は含まれません。そのため、労災の障害補償を受けても慰謝料を支払ってもらったことにならないので、加害者へ満額の慰謝料を請求することができます。また、後遺障害が残ったケースで慰謝料を受け取るには自賠責での「後遺障害認定」が必須となります。
交通事故に遭った際には、被害者が受傷したときに請求できる(後遺障害が残らなくても発生する)「入通院慰謝料」、被害者に後遺障害が残ったときに請求できる「後遺障害慰謝料」、被害者が死亡したときに請求できる「死亡慰謝料」の3種類の慰謝料が支払われます。
しかし、これらの慰謝料は、労災保険からは一切支給されません。そのため、交通事故の慰謝料は、加害者や加害者の保険会社に請求する必要があります。
労災申請の流れ

業務中や通勤中の事故等でケガを負ったとき、また、業務に起因して病気になったときも、労災保険により補償を受けることができます。労災保険は、労働者、またはその遺族の生活を守るための国が取り扱っている社会保険です。
労働災害としての補償を受けるためには、労働基準監督署(労基署)から認定を受ける必要があります。労災認定を受けることで、ケガの治療にかかる費用など、労災保険により一定程度の補償を受けることが可能になります。原則、労災申請の手続きは、ケガをされたご本人またはご遺族の方が行うことになっています。
① 労働災害(労災)が発生したことを会社に速やかに報告する。
労働災害が起きた場合、被災した従業員はまず会社に報告をします。仕事中に事故が発生しケガをした場合や通勤途中の事故によるケガの場合、ケガを負った労働者の名前、ケガを負った日時・時間、ケガの部位・状況などの事実を速やかに会社へ報告する必要があります。
② 病院を受診する。
受診の際、労災指定医療機関の病院窓口で労災であることを伝えれば、健康保険証を提示せずに治療を受けることができます。労災指定医療機関以外で治療を受けた場合には、治療費を自己負担で精算することになります。その場合には、労災であることを伝えて診断書を作成してもらいましょう。
③ 労働基準監督署(労基署)へ労災申請に必要な書類を提出する。
労災の事故報告を受けた事業主は、労災保険給付の請求書を作成して労働基準監督署長へ提出します。これは会社を通じて提出することも、従業員が直接労働基準監督署長に提出することも可能です。また、労災の申請は、業務災害か通勤災害かで提出する書類が違い、状況に応じた書類を各担当部署に提出する必要があります。
労災指定病院を受診する場合は、療養の給付請求書「様式第5号」が必要になり、受診する病院に提出します。(通勤災害の場合には様式第16号の3を提出。)
また、労災指定病院以外を受診する場合は、療養の費用請求書「様式第7号」が必要になり、治療を行なった病院ではなく、労働基準監督署に提出する必要があります。(通勤災害の場合には様式第16号の5を提出。)
休業補償を受ける場合は、「様式第8号」が必要となります。休業補償を請求する際に必要な請求書のことをいい、労働基準監督署に提出する必要があります。(通勤災害の場合には様式第16号の7を提出。)
提出する書類は、労働基準監督署や厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
④ 労働基準監督署による労災事故の調査が行われる。
労災の請求書が提出されたとしても、すぐに労災と認められるわけではありません。提出した書類をもとに、労働基準監督署によって、労働者や会社、治療を受けた医療機関などに対し聴き取り調査が行われます。
調査は、厚生労働省や労働基準監督署が定めた基準に基づいて行われます。
⑤ 労災保険の給付
調査が終わると労働基準監督署によって、労災か否かが判断され、労災に認定されると保険給付を受けることができます。
労災認定されず、その決定に納得ができない場合や不服がある場合は、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に審査請求をすることができます。この場合、申請が棄却されてから3か月以内に請求する必要があります。
労働災害と後遺障害・等級認定

業務または通勤の際に負ったケガや疾病の治療をしたものの、身体に一定の障害(後遺障害)が残っているとき、労働者の請求に基づいて、業務災害の場合は障害補償給付が、通勤災害の場合は障害給付が支給されます。
後遺障害は症状の程度に応じて14段階で区分されており、第1級から第14級までの等級があります。数字が小さいほど障害が重く、補償が手厚くなります。1級から7級については継続的に年金が支給される「障害(補償)年金」が、8級から14級については一時的に支給される障害(補償)一時金が支給されます。
障害等級表
第1級
・両目が失明したもの
・そしゃく及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢をひじ関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの
第2級
・一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
・両眼の視力が0.02以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
・両上肢を手関節以上で失ったもの
・両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
・一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
・そしゃく又は言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
・両手の手指の全部を失ったもの
第4級
・両眼の視力が0.06以下になったもの
・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力を全く失ったもの
・一上肢をひじ関節以上で失ったもの
・一下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両手の手指の全部の用を廃したもの
・両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
・一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
・神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・一上肢を手関節以上で失ったもの
・一下肢を足関節以上で失ったもの
・一上肢の用を全廃したもの
・一下肢の用を全廃したもの
・両足の足指の全部を失ったもの
第6級
・両眼の視力が0.1以下になったもの・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
・両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
・一上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・一下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
・一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
第7級
・一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
・両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
・一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
・一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
・一足をリスフラン関節以上で失ったもの
・一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
・両足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に著しい醜状を残すもの
・両側のこう丸を失ったもの
第8級
・一眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
・せき柱に運動障害を残すもの
・一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
・一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
・一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
・一上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・一下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
・一上肢に偽関節を残すもの
・一下肢に偽関節を残すもの
・一足の足指の全部を失ったもの
第9級
・両眼の視力が0.6以下になったもの
・位置眼の視力が0.06以下になったもの
・両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・一耳の聴力を全く失ったもの
・神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・一手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
・一手の母指を含み2の手指の用を廃したもの
・一足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
・一足の足指の全部の用を廃したもの
・外貌に相当程度の醜状を残すもの
・生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
・一眼の視力が0.1以下になったもの
・正面視で複視を残すもの
・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
・14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
・一上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
・一下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
・両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
・10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・せき柱に変形を残すもの
・一手の示指、中指又は環指を失ったもの
・一足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
・一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
・一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
・7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
・鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
・一上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・一下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
・長管骨に変形を残すもの
・一手の小指を失ったもの
・一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
・一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
・一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
・局部にがん固な神経症状を残すもの
・外貌に醜状を残すもの
第13級
・一眼の視力が0.6以下になったもの
・一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
・正面視以外で複視を残すもの
・両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
・5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
・一手の小指の用を廃したもの
・一手の母指の指骨の一部を失ったもの
・一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
・一足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
・一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
第14級
・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
・3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
・局部に神経症状を残すもの
【障害補償年金・傷害補償一時金】
障害補償年金、傷害補償一時金の金額は等級によって異なり、その金額は「給付基礎日額」に基づいて計算されます。「給付基礎日額」とは、「労災事故が発生した日から直前の3か月分の労働者に対して支払われた給料」を、「3か月分の日数」で割った額のことで、それぞれの等級に応じた日数分をかけることで、年金額を計算することができます。
障害補償年金
障害等級1~7級の場合、障害補償年金として、年金として給付が行なわれます。障害等級に応じて、当該障害が残る期間中、1年につき給付基礎日額の131~313日分が給付されます。
第1級:313日分
第2級:277日分
第3級:245日分
第4級:213日分
第5級:184日分
第6級:156日分
第7級:131日分
障害補償一時金
障害等級8~14級の場合、障害補償一時金として、給付額が一括払いされます。一時金のため、一度支払われたら支給は終わりとなり、給付基礎日額の56~503日分が支給されます。
第8級:503日分
第9級:391日分
第10級:302日分
第11級:223日分
第12級:156日分
第13級:101日分
第14級:56日分
弁護士に依頼するメリット

被害者の方にとって労災は初めての場合であることが多く、法的な知識がないと手続きはとても難しい作業です。弁護士に依頼をした場合には次のようなメリットがあげられます。
➀後遺障害が残った場合、弁護士に依頼すると適正な等級の後遺障害に認定される可能性が高まる
②労災保険の補償範囲を超える損害を受けた場合、弁護士に依頼すると慰謝料など適正な補償を受け取ることができる
➂示談交渉でストレスを感じている場合、弁護士に依頼すると難しい交渉から解放され、精神的にも不安が軽くなる
通勤災害の給付を受けるための手続きには、請求内容に応じた書式だけでなく、さまざまな資料の添付が必要です。スムーズな給付を受けるためには、書類をきちんと揃えることが重要になります。
損害賠償請求を検討されている方は、労災問題を取り扱っている弁護士への相談をおすすめします。

交通事故・労働災害に遭い、辛い出来事を体験された中でも、弁護士に相談しようと一歩を踏み出した方が、こちらの記事を読んで頂けていると思います。私も数年前に、親族を事故で亡くしました。大きな驚きと深い悲しみが今でも残っております。一歩を踏み出したあなたの想いを、是非受け止めさせてください。